「出前館って、バイクでも配達できるの?」
副業や働き方の自由さに魅力を感じつつ、バイクで始める場合のハードルや注意点が気になる…。そんな悩みをお持ちではありませんか?
- 原付・125cc・中型バイク、どこまで使える?
- バイク登録ってどうやるの?
- 保険は必要?ファミリーバイク特約でいいの?
- 自転車より本当に稼げるの?
実は、出前館のバイク配達は「効率よく稼ぎたい人」にとってかなり有利な選択肢です。
一方で、登録の仕方や保険の未加入によるペナルティなど、知らないと損する落とし穴も少なくありません。
この記事では、
- 配達に使えるバイクの種類と登録方法
- 必要な保険や書類、注意点
- バイク配達の収益性・維持費のリアル
- レンタルバイクで始める方法や費用感
…まで、出前館のバイク配達に必要な知識をわかりやすく解説します。
「バイクで出前館を始めてみたいけど不安が多い…」という方に向けて、準備から稼ぎ方まで一気に分かる内容です。 まずはチェックして、安心してスタートを切りましょう。
出前館配達員×バイクの基礎知識
出前館でバイク配達を始めるなら、車両の種類や登録ルールをしっかり把握しておくことが重要です。利用できるバイクの種類によって必要な書類が異なり、ルールを守らずに配達してしまうとアカウント停止のリスクも。ここでは、バイク配達に関する基礎知識を分かりやすくまとめました。
ざっくりとまとめると以下のとおりです。それぞれ見ていきましょう。
- 利用できるバイクは3種類
- 車両によって必要書類が変わる
- 勝手に配達車両を変えるのはNG
利用できるバイクは3種類
出前館では、バイクを使った配達が可能です。対応しているバイクは主に以下の3タイプ。
- 原付バイク(50cc以下):手軽に始めたい人におすすめ。ファミリーバイク特約でもOKな場合が多く、任意保険のハードルが低めです。
- 小型バイク(51〜125cc):取り回しが良く、スピードも出やすいので、エリアによっては最も効率的な選択肢に。
- 中型以上バイク(126cc超):長距離エリアでの配達や、バイクを趣味にしている人には◎。ただし保険や車検など、必要書類が一気に増える点に注意。
どのバイクでも配達は可能ですが、登録時に正しい情報を出さないと後々トラブルのもとになります。
車両によって必要書類が変わる
出前館にバイクで登録する場合、使用するバイクの種類によって必要書類が異なります。
- 車両登録証明書(軽自動車届出済証など)
- 自賠責保険証明書
- 任意保険証券(業務使用可が明記されたもの)
- ナンバープレートの写真
原付ならファミリーバイク特約でもOKな場合がありますが、業務使用が可能かどうかは保険内容を必ず確認しましょう。「通勤通学用」だけだとNGです。
なお、登録手続きの際にアップロードした情報に不備があると、審査に落ちることもあるので、丁寧にチェックしておきましょう。
勝手に配達車両を変えるのはNG
「登録は自転車だけど、今日はバイクでやっちゃおう」──これは絶対にやってはいけません。
出前館では、申請した車両以外での配達は禁止されています。もし発覚すると、警告だけで済まず、アカウント停止(通称:垢バン)の対象になることも。
バイクに切り替えたい場合は、きちんとアプリから車両変更申請を出しましょう。変更手続きには数日かかることもあるので、早めの申請をおすすめします。
ちなみに、登録内容と実際の使用車両の整合性は、事故が起きた時や保険適用時に大きな問題になります。「バレなければOK」では済まされません。
出前館の配達で使えるバイクの種類と条件
出前館の配達でバイクを使いたい方に向けて、原付から中型以上まで、それぞれの特徴や登録時に必要な書類、向いている働き方を解説します。どのバイクを選ぶかで、配達のしやすさや稼ぎやすさが大きく変わるので、自分のエリアやライフスタイルに合った選択が重要です。
ざっくりとまとめると以下のとおりです。それぞれ見ていきましょう。
- 原付(50cc以下)
気楽に始められる。原付き特有の交通ルールあり(制限速度30km、二段階右折あり など)。 - 125cc以下のバイク
バイク配達の中ではコスパ最強説。原付きのような交通ルール上の制限なし - 125cc超のバイク
長距離エリアでの配達で有利。ただし車両の購入費や維持費が最もかかりやすい。また緑ナンバーの取得も必要で気軽さの側面では劣る。
原付(50cc以下)
メリット・特徴
原付は、出前館の配達でいちばん手軽に始められるバイクタイプです。街乗りに適していて、小回りがきくため、都市部の短距離配達に最適。
- 維持費が安く、燃費も良好
- ファミリーバイク特約が使える可能性が高い
- 自転車より疲れにくく、スピードも出る
デメリット・注意点
一方で、原付特有のルールや制限にも注意が必要です。
- 最高速度30km/hの制限あり(速度超過で違反切符も)
- 二段階右折のルールに慣れが必要
- 坂道・長距離は少ししんどい
登録時に必要になる書類
- 軽自動車届出済証(ナンバープレートが登録されている証明)
- 自賠責保険証明書
- 任意保険証(ファミリーバイク特約でもOKな場合あり)
- ナンバープレート写真
おすすめのバイク
- ホンダ トゥデイ:シンプルで壊れにくい定番
- ヤマハ JOG:軽くて扱いやすい、女性にも人気
125cc以下のバイク
メリット・特徴
通称「原付二種」に該当するバイクで、原付よりスピードや安定性が高く、バイク配達の中ではコスパ最強と言われるクラスです。
- 最高速度制限なし、流れに乗って運転できる
- 二段階右折不要
- 長距離配達も可能で効率が良い
デメリット・注意点
- 原付より初期費用・維持費はやや高め
- 一部のファミリーバイク特約が適用されないことも
登録時に必要になる書類
- 軽自動車届出済証
- 自賠責保険証明書
- 業務使用が明記された任意保険証
- ナンバープレート写真
おすすめのバイク
- ホンダ PCX125:積載性と快適性を両立
- スズキ アドレスV125:軽量で加速も◎
125cc超のバイク
メリット・特徴
中型・大型バイクの部類で、長距離配達や郊外エリアでの配達に向いています。
- 高速走行が可能でエリアを広くカバーできる
- 積載量が多く、箱を大きくしても安定する
デメリット・注意点
- 車両の購入費用が高い
- 維持費・任意保険料が高い
- 「事業用ナンバー(緑ナンバー)」が必要になるケースあり
- 都市部の配達では小回りがきかず非効率なことも
登録時に必要になる書類
- 自動車検査証(車検証)
- 自賠責保険証明書
- 業務使用可能な任意保険証(明記必須)
- 「貨物軽自動車運送事業」の届出が必須(緑ナンバーが必要)
- ナンバープレート写真
おすすめのバイク
- ホンダ フォルツァ:高速道路も使える万能スクーター
- ヤマハ NMAX155:都市と郊外の両立を目指す人向け
どのバイクがベストかは、「配達エリア」「距離」「報酬効率」「体力」「保険料」など総合的に見て決めるのがポイントです。
出前館のバイク登録の流れと手順
出前館でバイク配達を始めたい場合、アプリ上での登録から必要書類の提出、審査通過までいくつかのステップを踏む必要があります。特に書類の不備は審査落ちの原因になるため、事前に流れを把握しておくのが安心です。この章では、登録手順をわかりやすく解説します。
ざっくりと手順をまとめると以下のとおりです。それぞれ見ていきましょう。
- 出前館アプリ/マイページで「バイク登録」を選択
- 必要書類をアップロード(免許証、車検証、保険証書)
- 審査完了後にバイクでの稼働が可能になる
▼出前館アプリ/マイページで「バイク登録」を選択
まずは出前館の配達員専用アプリ、またはWEBのマイページにログイン。メニュー内の「車両登録」から、使用する車両タイプを選択します。バイクでの配達を希望する場合は「原付」「バイク(125cc以下/以上)」など、該当するタイプを選びましょう。
▼必要書類をアップロード(免許証、車検証、保険証書)
登録申請を進めるには、バイクの使用に必要な書類のアップロードが求められます。
- 運転免許証(有効期限内のもの)
- 自賠責保険証明書
- 任意保険加入証明書(ファミリーバイク特約可)
- 車検証または軽自動車届出済証
- ナンバープレート写真(番号が鮮明に写っているもの)
バイクの種類によって若干書類が異なりますが、すべて「業務利用」として保険がカバーされているか確認が必要です。
原付でも「任意保険加入証明」は必須
「原付なら自賠責だけでいいんじゃ?」と思いがちですが、出前館では任意保険加入証明の提出が必須です。事故や損害賠償リスクを考慮すると、これは非常に大事なポイント。
ファミリーバイク特約を活用するなら、加入証明に対象車両のナンバーが記載されていることを確認しましょう。
▼審査完了後にバイクでの稼働が可能になる
書類をすべて提出すると、出前館側で審査が行われます。問題がなければ通常2〜3営業日以内で承認が下り、その後バイクでの稼働が可能になります。
ただし、書類不備や写真が不鮮明な場合は差し戻されることもあるため、提出時は丁寧にチェックしましょう。
自転車→バイクへ変更する場合の注意点
マイページで車両変更申請が必要(再審査あり)
すでに自転車で配達していて「これからはバイクで稼働したい!」という場合は、マイページから「車両変更申請」を行う必要があります。
この申請には再度の審査があるため、初回登録時と同じく必要書類をアップロードする準備が必要です。
新たに保険書類・車両証明書の再提出が必要になる場合も
変更申請時には、次のような書類の再提出が求められます。
- 任意保険証明書(業務利用が記載されたもの)
- バイクのナンバープレート画像
- 自賠責保険証明書・車検証など
配達用に保険が適用されていない場合は審査に通らないので、契約内容を確認しましょう。
変更中は稼働できないタイミングが発生する可能性あり
車両変更の申請を出してから審査が完了するまでの間、出前館側の仕様上、稼働ができない期間が発生することもあります。
そのため、変更を申請するタイミングは「稼働予定の少ない日」や「週明け」など、余裕のある日程を選ぶのがおすすめです。
また、稼働再開後に新しい車両で配達を始めたタイミングでアプリ内の設定を忘れず更新しておきましょう。無登録車両での配達はアカウント停止のリスクがあるので要注意です。
出前館バイク配達に必要な保険とおすすめの選び方
出前館で自転車からバイクへ切り替えたい場合は、ただ乗り換えるだけではNG。正式な「車両変更申請」と再審査が必要になり、書類の再提出や稼働停止期間が発生することもあります。スムーズに変更するための注意点を、事前にしっかり把握しておきましょう。
ざっくりとまとめると以下のとおりです。それぞれ見ていきましょう。
- マイページで車両変更申請が必要(再審査あり)
- 新たに保険書類・車両証明書の再提出が必要になる場合も
- 変更中は稼働できないタイミングが発生する可能性あり
原付向け:ファミリーバイク特約
原付バイク(50cc以下)を使って出前館で配達する場合、一番手軽なのがファミリーバイク特約。これは、自分や家族が加入している自動車保険に付けられる「オプション保険」です。
- 親や配偶者が車の保険に入っていれば追加で加入できる
- 月数百円〜とコスパ最強
- 他人の原付を使っていても補償されるケースもある
ただし注意点もあります。契約者本人が対象になっていなかったり、「業務使用」が対象外になっている保険もあるので、必ず保険会社に『業務で使うけど補償されるか?』と確認しましょう。
125cc以上向け:業務使用対応の任意保険
125ccを超えるバイクを使う場合は、ファミリーバイク特約が使えません。この場合は、自分で任意保険(業務使用対応プラン)に加入する必要があります。
- 「通勤・業務使用OK」のプランを選ぶことが重要
- 個人利用の保険だと、配達中の事故は補償対象外になることが多い
- 加入時は「出前館で業務使用します」と明確に伝える
また、補償の穴を埋めるなら、損害賠償保険系のサービスを併用するのもありです。たとえば「フリーナンス」は、フリーランス向けに業務中の賠償責任をカバーする保険が付いており、月500円程度で加入できます。
任意保険と組み合わせておくと、万が一のときも精神的にかなり安心できます。
バイクの購入が厳しい人はバイクレンタルが◎
バイクを持っていなくても出前館で配達を始めたい方には、レンタルバイクの活用がぴったり。初期費用を抑えつつ、装備や保険込みでスタートできるのが魅力です。ただし、契約内容には注意点もあるため、事前にしっかり確認しておくことが大切です。
ポイントをざっくりとまとめると以下のとおりです。それぞれ見ていきましょう。
- 出前館提携の「仕入館」で格安レンタルが可能
- 契約条件や距離制限、免責事項もチェック
出前館提携の「仕入館」で格安レンタルが可能
出前館と提携している「仕入館」では、配達員向けに配達用装備込みでのレンタルバイクを提供しています。
- 月額1.5万円〜3万円ほどでバイクが借りられる
- 配達BOX・スマホホルダーなどが初期セットで装備済み
- 任意保険込みで安心してスタートできる
しかもメンテナンスや故障時の対応も含まれているため、「整備が苦手」「バイクは壊れたら困る…」という方にも安心。出前館公式の連携先というのもポイントです。
契約条件や距離制限、免責事項もチェック
とはいえ、レンタルには以下のような注意点もあります。
- 月間の走行距離に上限があるプランもある
- 契約期間の縛りや解約金の有無を確認すること
- 事故時の自己負担額(免責額)を事前に把握しておく
「とにかくバイクで始めたいけど、買うのはちょっと…」という方にはぴったりですが、契約前に細かいところまでチェックしておきましょう。
配達効率をグッと上げたいなら、バイク配達は本当に強力な選択肢。ただし、保険や車両登録の部分を適当に済ませると後々トラブルになることも多いので、安全第一でスタートしてくださいね。
バイク配達は稼げる?結論:自転車より稼げる
バイク配達は出前館でしっかり稼ぎたい人にとって、非常に効率の良い選択肢です。移動スピードが速く、件数もこなしやすいため時給アップに直結。長距離配達やダブル配達にも強く、体力的にも自転車より余裕があります。コスト面でも車よりバランスが良く、収益性の高さが魅力です。
ポイントをまとめると以下のとおりです。それぞれ見ていきましょう。
- 1時間あたりの配達件数が伸びやすい=時給アップに直結
- 長距離エリアや2件同時配達で報酬UPが狙える
- 自転車より疲れずに長時間稼働できる
- 車と比べると維持費・登録コストが安く、バランスが良い
1時間あたりの配達件数が伸びやすい=時給アップに直結
出前館でバイク配達を始めると、まず実感するのが「配達件数が増える」ということ。やっぱり移動スピードが全然違います。
自転車だと1時間に2~3件が限界でも、バイクなら4件以上狙えることも。1件あたりの単価が高い出前館では、この違いが時給にそのまま反映されます。
長距離エリアや2件同時配達で報酬UPが狙える
出前館は距離に応じて配達報酬が上がるシステム。つまり、長距離のオーダーは報酬が高めなんですが、これを安定して受けられるのがバイク配達の強みです。
さらに、2件同時配達(ダブル)もやりやすいので、1時間あたりの売上がグッと上がります。
自転車より疲れずに長時間稼働できる
「今日は3時間だけにしとこうかな…」と自転車配達で体力が限界になっていた人も、バイクなら5~6時間ぶっ通しで走れてしまうことも多いです。
この「疲れにくさ」は、稼働時間を延ばしたい人にとって大きなメリット。結果的に月の報酬も伸びやすくなります。
車と比べると維持費・登録コストが安く、バランスが良い
「車も考えたけど、コスト面で悩んでいる…」そんな方には、バイクがまさにちょうどいい選択肢。
- 燃料費が車より安い
- 駐車スペースに困らない
- 車検不要(原付や125cc以下の場合)
車と比べるとコストが抑えられ、それでいて稼働効率はかなり高いという、“いいとこ取り”ができるのがバイクです。
バイクで出前館配達を始める前に知っておきたい注意点
バイクで出前館の配達を始めるなら、効率の良さだけでなくリスク面にも目を向けておく必要があります。事故や違反によるアカウント停止、ヘルメット未着用などのルール違反、さらには燃料代や整備費といったコスト負担も発生します。安全に長く働くために、始める前に必ず確認しておきましょう。
ざっくりとまとめると以下のとおりです。それぞれ見ていきましょう。
- 事故や違反は自己責任+アカウント停止リスクあり
- ヘルメット未着用・ナンバー不備は即BAN対象
- 燃料代・整備費用で月1万円前後発生することを見込む
- 「業務委託」としての自覚を持ち、安全運転を徹底する
事故や違反は自己責任+アカウント停止リスクあり
出前館は「業務委託契約」なので、事故や違反があったときはすべて自分の責任になります。
さらに、重大な違反や事故があった場合はアカウント停止(いわゆる“垢BAN”)のリスクも。安全運転と交通ルールの遵守は、稼ぐための大前提です。
ヘルメット未着用・ナンバー不備は即BAN対象
軽く考えてしまいがちな部分ですが、ヘルメットの未着用や、登録と違う車両の使用は即アカウント停止の対象になることもあります。
- ヘルメットは必ず着用(法律上の義務)
- 登録したナンバーと違うバイクでは絶対に稼働しない
たった一度の油断で稼働停止…なんてことにならないよう、基本的なルールはしっかり守りましょう。
燃料代・整備費用で月1万円前後発生することを見込む
バイク配達は稼げる一方で、“維持費”というコストが発生するのも忘れてはいけません。
- ガソリン代:5,000~8,000円前後/月
- オイル交換・整備費:数千円/月
つまり、配達で月5万円稼いでも、そこから1万円近くが引かれるイメージ。
自転車と違って「維持費を超える売上を上げないと儲けが出ない」という構造になるため、売上とコストの両面で計算することが大切です。
「業務委託」としての自覚を持ち、安全運転を徹底する
出前館の配達員は社員ではなく、個人事業主扱い。つまり事故や違反をしても守ってくれる「会社」は存在しません。
だからこそ、自分で安全に気を配ること、そして保険の加入や登録の正確性など、“自分の責任で働く”意識を持つことが非常に大切です。
まとめ|出前館のバイク配達は効率よく稼ぎたい人に最適!
- 登録手順・保険・車両条件をクリアすれば効率よく稼げる
- バイク配達は中・長距離エリアや長時間稼働に向いている
- 違反や保険未加入リスクに気をつければ、安全・高収益が実現可能
- 「自転車で限界を感じている人」はぜひステップアップを検討しよう
体力的な負担を減らしつつ、より多くの配達件数をこなして収入をアップしたいなら、バイク配達は非常に魅力的な選択肢です。
ただし、ルールや保険の確認を怠るとトラブルの原因になることも。きちんと準備したうえで、バイク配達ライフをスタートさせましょう!
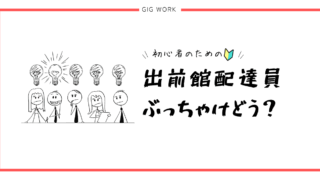
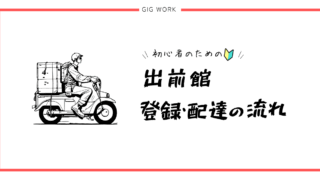
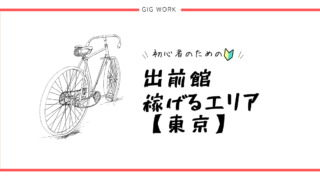
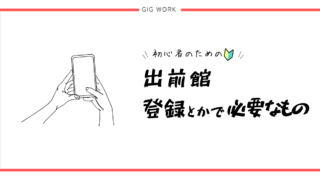
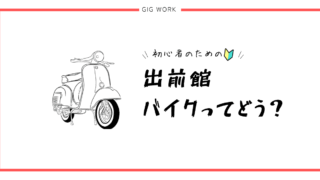
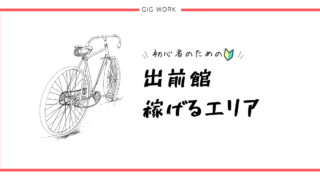
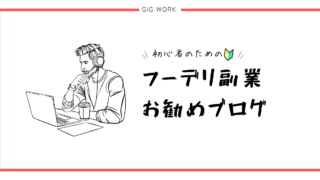
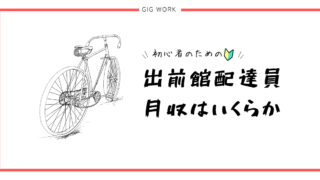
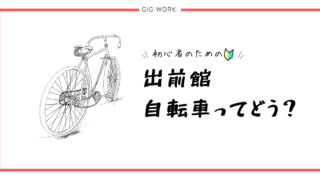
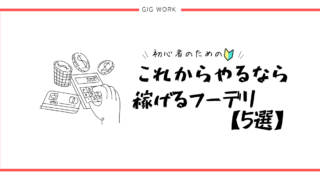
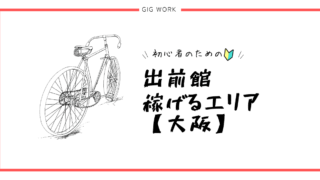

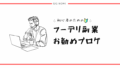

コメント